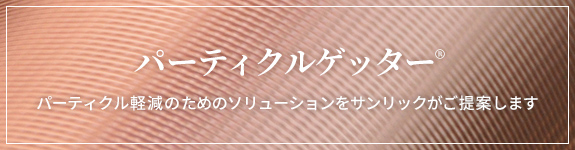サンリックコラム
vol.04
レアメタルの話や業界のトレンド、サンリックの日常など、ざっくばらんなテーマをコラム形式で掲載していきます。不定期更新。

有機EL研究は真空蒸着機がなければ始まらない。
それはまるで、包丁のない料理人、ペンのない作家みたいなものだ。要するに何もできない。
そんな時に、ニューヨーク州ロングアイランド、ブルックヘブン国立研究所にいる知人が真空蒸着機を持っているという情報を耳にした。すぐさまファックスを送り、何度かのやりとりの末、「夏の2カ月、好きに使っていい」と話が決まった。
そのとき私は、彼にこう囁いたのだ。 「有機ELは面白いよ。目新しくて金にもなるかもしれん」
と甘い言葉を並べ立てた。 すると彼は、渡航費も滞在費も出してくれるという。年間5万円しか研究費が支給されない極貧助手にとってこれは大きい。
国立研究所とはいえ、研究室にあるのはオイル拡散ポンプ付きの真空蒸着機。旧式で、ごく簡素なものだった。だが、独り占めできる夢にまで見た蒸着機。これはもう、幼い日に初めて手にした自転車のような歓び、あるいは大学生が親から初めて車を買ってもらった時の興奮に近かった。
朝は化学実験室で材料を合成し、午後からは蒸着機の前に張りつく。眠るのは4時間ほど。
まるで東大受験生のような生活。だが、不思議なことに苦痛ではなく、むしろ幸福だった。徹マンしている時の学生の気分か。
とはいえ、私は“真空素人”だった。師も、手ほどきしてくれる先輩もいない。あるのは己の好奇心だけ。たとえば、陰極材料。Tangたちの有名な論文では、ITO(インジウム・スズ酸化物)陽極とMg(マグネシウム):Ag(銀)合金の陰極が用いられている。 だが、不親切にも「なぜ陰極はその組み合わせか、なぜその比率か」は書かれていない。しかも、こちらの装置は蒸着用電源がたったひとつ。2種の金属を同時に蒸着する共蒸着は不可能。
ならば、とMgだけで作ってみた。光ったり、光らなかったり。再現性がない。中学生の夏休みの自由研究と大差ない。
Agだけで試すと、今度は駆動電圧が馬鹿みたいに高く、光らぬ。 私は夜のラボでつぶやいた。
「Tangさんよ……なぜ10:1で混ぜる必要があるんですかねえ?」
苦し紛れに、Mgを薄く蒸着し、その上にAgを重ねてみた。
するとどうだ。 光った。 しかも、何度やっても、ちゃんと光った。
深夜。静寂の中、思考だけがギラついていた。
「なるほど、Mg単体では有機物の上で密着性が低く安定しない。Agが“錨”となってMgを繋ぎ止めているのか」
そもそも陰極からの電子注入は、化学的には、電極界面での有機分子の還元反応。重要なのは、有機物と電極の“界面”だ。
バルクの金属は電流を流すだけ、一番重要なのは、界面で何が起きるか。ならば、Mgよりもっと仕事関数の小さい、すなわち還元力のある金属を使えば、もっと低電圧で光るのでは?
そう思い至った。
それで目をつけたのが、Li(リチウム)だった。
反応性が高く、大気中ではすぐ酸化してしまう。有機合成反応でも使う「取り扱い注意」の危険物。 だが、もしこいつで成功すれば、有機ELの駆動電圧がさらに下がる。
そう考えると、ドミトリーに帰って寝る気も起きなかった。
まずLiを20nm成膜し、その上から電極になるAgを厚く100nm蒸着する。素子が完成し、私はスイッチに指をかけ、思わず口元を歪めた。「フフフ……」と、まるでマッドサイエンティストのように。
スイッチオン──何も起きない。
光らない。真っ暗。
「おいおい、仕事関数って何だったんだ。私の何が悪いのよ。」
肩を落としながらも、じっと素子を眺めると、5ミリ角の四角い素子の一片だけが細くしかも明るく光っている。 それは、まるで襖の隙間から差し込む朝の光のようだった。
10分ほど、私は考えた。
チンパンジーより若干大きめの脳みそをフル回転させた。
蒸着チャンバーの中で、LiとAgのそれぞれが入った二つの坩堝は基板の真下にはない。
どちらも若干中心からずれて配置されており、有機膜の上には発光エリアをパター二ングするために0.5mmの厚みの金属マスクがある。
となれば、マスクの影になる部分ではLiが回り込んで極めて薄く付着しているのだろうか。
つまり、極薄のLi層が、光るカギに違いない。
東の空が白むまで、私は膜厚を減らし続けた。 半分に。さらに半分に。そして最後は1nmほど。
そして、スイッチオン。
光った。
しかも、これまで見たことのない低電圧で、 3000cd/m2を超える輝度。 目がくらむほどだった。
思わず声が漏れた。
ワオ、、
この陰極界面層を用いる二層型陰極構造──当時、Tangらの論文の呪縛に縛られ、金属共蒸着電極ばかり使われていた時に、極貧だったからこそ行き着いたアイデアだった。 今でこそ、Liだけでなく、LiFやリチウム錯体が陰極界面層として使われているが、あのとき私は、ただの素人、デバイスの初心者。だが、妄想じみた想像力だけが唯一の武器だった。
そしてそれが、通じた。
いい時代だった。
つづく。
寄稿:山形大学 フェロー 城戸
お問い合わせ
設計から加工、製造、そして分析、サポートまで一貫して対応できる体制を
整えておりますので、お気軽にご相談ください。
- 製品・材料に関するお問い合わせは
- Tel. 045-522-8989
Fax. 045-522-8993
- その他のご用件は(代表電話)
- Tel. 045-522-8988(代表)
代表Fax. 045-522-8992